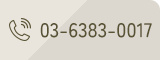歯科口腔外科
 口腔外科では主に、親知らずの抜歯や顎関節症の治療、口内炎などの口腔粘膜疾患、歯の破折や裂傷といった外傷など、外科的な処置が必要な口腔トラブルに対応しています。
口腔外科では主に、親知らずの抜歯や顎関節症の治療、口内炎などの口腔粘膜疾患、歯の破折や裂傷といった外傷など、外科的な処置が必要な口腔トラブルに対応しています。
当院には日本口腔外科学会認定医が在籍しており、抜歯や外傷などの治療においても、顎の骨への影響や神経損傷を避けるため、精密な診断と慎重な処置を行っています。
また、口腔がんや前癌病変などを早期に発見するためには、口腔内のわずかな異変も見逃さない的確な診断と適切な対応が求められます。
こうした処置には、担当医の高度な技術と専門的な知識、そして豊富な経験が不可欠です。
正確な診断を行える歯科医師と、安全な治療を支える設備が整った歯科医院を選ぶことが大切です。
親知らず
親知らずとは、10代後半〜20代前半に1番奥(前歯から数えて8番目)に生えてくる歯のことです。親知らずは左右上下4本生えてくる方と、数本しか生えてこない方、1本も生えてこない方など、人によって生え方はさまざまです。
親知らずは必ず抜歯しなければいけないわけではありませんが、痛みや腫れが生じている場合や、むし歯や歯周病の原因になっている場合、他の歯や歯列に悪影響を及ぼしている場合、口腔粘膜を傷つけている場合などには早めに治療する必要があります。痛みなどがなくても、親知らずが生えてきたら一度歯科医院で状態をチェックしておくことをおすすめします。
当院では、歯科用CTを用いて親知らずの生え方や周辺の歯や周辺組織への影響などを正確に診断し、抜歯後の腫れや痛みを最小限に抑えた精密な治療を行っています。親知らずの抜歯について分からないことや不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
歯科用CTを用いた精密な診断と安全な親知らずの抜歯
 当院では安全性の高い精密な親知らずの抜歯を行うために、歯科用CTを導入しています。
当院では安全性の高い精密な親知らずの抜歯を行うために、歯科用CTを導入しています。
親知らずは人によって生えている本数が違うだけでなく、生え方もそれぞれ異なります。斜めに生えている場合や横向きに生えている場合、埋もれている場合など状態はさまざまで、抜歯に適したタイミングや治療方法もそれぞれ異なります。
そのため、親知らずの抜歯前には精密な診断を行うことが非常に重要です。 歯科用CTを用いた3次元画像では、親知らずの生えている位置や方向、親知らず周辺の神経や血管の走行位置などを正確に把握することが可能です。歯科用CTでの精密な診断を行うことは、余分な切開や神経損傷リスクを回避し、患者さまの身体的・精神的な負担を大幅に軽減することにつながります。
親知らずを放っておくリスク
① 親知らずのむし歯や歯周病、智歯周囲炎になりやすい
親知らずは1番奥に生えるためデンタルケアが不十分になりやすく、むし歯や歯周病、智歯周囲炎などを引き起こしやすいです。これらは進行すると歯を支える骨にも影響を及ぼすため、痛みや炎症がある場合には抜歯をすることをおすすめします。
② 親知らずの周囲の歯にもトラブルが生じる
親知らずにむし歯や歯周病などのトラブルが生じていると、やがて親知らずの手前の歯(第二大臼歯)にも細菌が侵食するおそれがあります。第二大臼歯は顎のかみ合わせにも大きな影響を与えるため特に大切にしてほしい歯です。
また、第二大臼歯に長い期間圧力がかかっていると、歯根が溶けてしまう「吸収現象」が起き、抜歯リスクを高めます。周囲の歯やかみ合わせに悪影響を及ぼす危険性がある場合には、親知らずの抜歯を早めに行うことをおすすめします。
抜歯が必要なケース
次のような親知らずは、抜歯をおすすめします。
①他の歯を圧迫している親知らず
 顎が小さく親知らずが生えるためのスペースが不足していると、真っ直ぐ生えることができず、斜めや横向きに生えて隣接する歯を圧迫してしまう場合があります。圧力が継続的にかかっていると、歯列を乱すおそれや、隣接する歯の歯根を溶かしてしまうおそれがあるため、抜歯をおすすめします。
顎が小さく親知らずが生えるためのスペースが不足していると、真っ直ぐ生えることができず、斜めや横向きに生えて隣接する歯を圧迫してしまう場合があります。圧力が継続的にかかっていると、歯列を乱すおそれや、隣接する歯の歯根を溶かしてしまうおそれがあるため、抜歯をおすすめします。
② 歯肉の下に埋もれている親知らず
 一部が歯肉に埋もれて生えている親知らずは、汚れが溜まりやすく、細菌が増殖しやすいためむし歯や歯周病の発症リスクが高まります。また、完全に埋もれている親知らずも、歯肉の下で炎症が起きやすく感染症を引き起こしやすいため、抜歯をおすすめします。
一部が歯肉に埋もれて生えている親知らずは、汚れが溜まりやすく、細菌が増殖しやすいためむし歯や歯周病の発症リスクが高まります。また、完全に埋もれている親知らずも、歯肉の下で炎症が起きやすく感染症を引き起こしやすいため、抜歯をおすすめします。
③ かみ合わせに影響がある親知らず
 斜めや横向きに生えている親知らずが原因で、かみ合わせに乱れが生じている場合には抜歯をおすすめします。かみ合わせの不調は、歯だけでなく顎関節や全身にさまざまな負担をかけますので、悪化する前に早めに治療することが大切です。
斜めや横向きに生えている親知らずが原因で、かみ合わせに乱れが生じている場合には抜歯をおすすめします。かみ合わせの不調は、歯だけでなく顎関節や全身にさまざまな負担をかけますので、悪化する前に早めに治療することが大切です。
顎関節症
 顎関節症とは頭蓋骨と下顎骨つなぐ関節のことで、口の開閉動作や咀嚼に関係します。
顎関節症とは頭蓋骨と下顎骨つなぐ関節のことで、口の開閉動作や咀嚼に関係します。
この顎関節や咀嚼筋などの周辺組織に痛みや違和感を感じたり、口を開け閉めするとカクカクと音が鳴ったり、大きな口を開けられないなどの症状がある場合には顎関節症の可能性があります。
顎関節症は放置していると、肩こりや首こり、頭痛、めまいなどの全身症状を招くおそれがあるため、早めに治療するようにしましょう。
顎関節症の原因は主にストレスや生活習慣、かみ合わせ、歯ぎしりや食いしばり癖などが影響していると言われています。患者さま一人ひとりの状態に適した治療を行いますので、顎関節症の心配がある方はまずはお気軽にご相談ください。
顎関節症の症状
- 口を開け閉めするとカクカクやゴリゴリと音が鳴る
- 口を大きく開けることができなくなった、スムーズに開閉できない
- 顎関節やその周辺に痛みや違和感がある
- 硬いものを噛むと痛みが増す、痛みで噛めない
- かみ合わせが急に変わった、違和感がある
- 慢性的な肩こりや頭痛がある
治療法
スプリント療法(マウスピース)
 スプリント療法は、顎関節にかかる負担を軽減することを目的に行う治療方法で、睡眠中にスプリント(マウスピース)を装着することで咀嚼筋の緊張を和らげます。 スプリントは顎関節症の症状を緩和するために作られたマウスピースなので、歯ぎしりや食いしばりの際に使用するナイトガードよりもかみ合わせの調整を重視したマウスピースになっています。
スプリント療法は、顎関節にかかる負担を軽減することを目的に行う治療方法で、睡眠中にスプリント(マウスピース)を装着することで咀嚼筋の緊張を和らげます。 スプリントは顎関節症の症状を緩和するために作られたマウスピースなので、歯ぎしりや食いしばりの際に使用するナイトガードよりもかみ合わせの調整を重視したマウスピースになっています。
当院では患者さまの歯形に合ったオーダーメイドのスプリントを作製し、それぞれのかみ合わせに合わせて調整を行っています。
かみ合わせ治療
むし歯による歯の欠損がある場合にはむし歯治療を行い、詰め物や被せ物の適合性が悪い場合や劣化がある場合には、詰め物や被せ物の再治療を行うことでかみ合わせを整えます。
ほんのわずかな高さのズレでもかみ合わせは乱れることがありますので、0.1ミリ単位で微調整を行います。正しいかみ合わせになることで、顎関節症の症状が改善する可能性があります。
外傷
スポーツ中の転倒や衝突、交通事故などで歯の破折や口腔粘膜の裂傷が生じた場合には、できるだけ早く歯科医院をご受診ください。
お口の中の傷をそのまま放置していると細菌感染を起こすおそれがあります。
さらに、歯に衝撃を受けた場合、歯の神経や顎の骨にもダメージが及んでいる可能性もあります。当院では、必要に応じてレントゲンなどの精密検査を行い、骨や神経に損傷がないか慎重に確認いたします。
また、歯が大きく欠けてしまった場合や、抜けてしまった場合には、歯を乾燥しないよう保存液か牛乳などに漬けて持ってきてください。早くに適切な処置を行うことができれば、元に戻せる場合もございます。